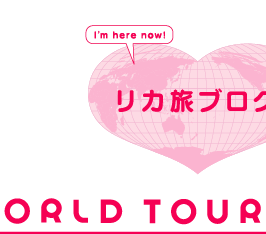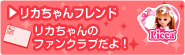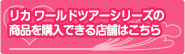名前:香山リカ
誕生日:5月3日
星座:牡牛座
身長:142cm
体重:34kg
誕生日:5月3日
星座:牡牛座
身長:142cm
体重:34kg
-
「 クリスマスの奇跡!」 -
「 サンタさん・・・・・・?」 -
「 ここは、森と湖の国。」 -
「 初ライブは大成功!」 -
「 わたしのそら。」
龍(りゅう)の鳴き声?
2007.10.06[Sat]19:39

しーんとした静けさにつつまれる
木立にかこまれた境内(けいだい)を歩き、お堂の中へ。
一歩足をふみいれると、天井いっぱいに描かれた
大迫力の「蟠龍図(ばんりゅうず)」。
お寺の方が「この場所に立って手をたたいてください」と、
ひとりひとりを案内してくれています。
私の前のおじさんとおばさんが、ふたりいっしょに手をたたこうとすると、
「おひとりずつどうぞ。少しでも位置がズレると、
もう聞こえないんですよ」と、言ったのです。
そして、いよいよ私の番。
天井を見上げて、手をあわせて、パン、パン、パン。
すると、なぜかふしぎな音が返ってきました。
カラカラカラカラ、カラカラカラカラ・・・・・・。
鈴をころがしたように、音が何重にもかさなりあってひびきます。
なのに、すぐとなりに立っているお寺の方から、
「ちゃんと聞こえましたか?」と確認されました。
つまり、となりに立っている人には、もう聞こえないのです。
なんて、ふしぎな絵なんだろう!
この龍は、およそ400年も前に描かれたもの。
日本でいちばん古いこのお堂は、龍にずっと守られていたんですね。
〈龍の絵のふしぎ〉
龍の下で手をたたくと、天井に反響して
やまびこのようにカラカラと音が返ってくることから、
別名「鳴き龍(りゅう)」とも呼ばれています。
手をたたく人によって音が変わり、高い音、低い音、
力強い音、やさしい音・・・・・・と個性があるそうです。
この天井絵は、足利義満(あしかがよしみつ)という室町時代の将軍様が
建てた「相国寺」(しょうこくじ)で見られます。


相国寺の「空中の間」にて。

こんなところにゾウさんの絵が!
昔の人はゾウを見たことがなかったので、これは想像して描いたんだって!
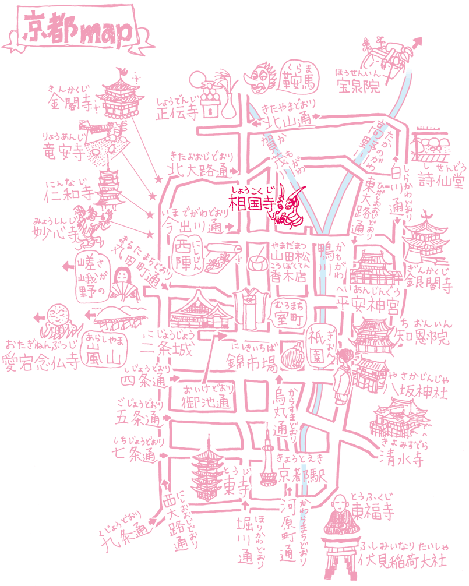
木立にかこまれた境内(けいだい)を歩き、お堂の中へ。
一歩足をふみいれると、天井いっぱいに描かれた
大迫力の「蟠龍図(ばんりゅうず)」。
お寺の方が「この場所に立って手をたたいてください」と、
ひとりひとりを案内してくれています。
私の前のおじさんとおばさんが、ふたりいっしょに手をたたこうとすると、
「おひとりずつどうぞ。少しでも位置がズレると、
もう聞こえないんですよ」と、言ったのです。
そして、いよいよ私の番。
天井を見上げて、手をあわせて、パン、パン、パン。
すると、なぜかふしぎな音が返ってきました。
カラカラカラカラ、カラカラカラカラ・・・・・・。
鈴をころがしたように、音が何重にもかさなりあってひびきます。
なのに、すぐとなりに立っているお寺の方から、
「ちゃんと聞こえましたか?」と確認されました。
つまり、となりに立っている人には、もう聞こえないのです。
なんて、ふしぎな絵なんだろう!
この龍は、およそ400年も前に描かれたもの。
日本でいちばん古いこのお堂は、龍にずっと守られていたんですね。
〈龍の絵のふしぎ〉
龍の下で手をたたくと、天井に反響して
やまびこのようにカラカラと音が返ってくることから、
別名「鳴き龍(りゅう)」とも呼ばれています。
手をたたく人によって音が変わり、高い音、低い音、
力強い音、やさしい音・・・・・・と個性があるそうです。
この天井絵は、足利義満(あしかがよしみつ)という室町時代の将軍様が
建てた「相国寺」(しょうこくじ)で見られます。


相国寺の「空中の間」にて。

こんなところにゾウさんの絵が!
昔の人はゾウを見たことがなかったので、これは想像して描いたんだって!
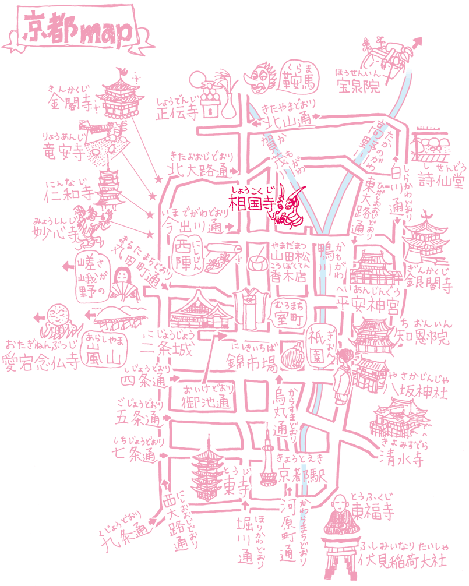
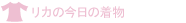 |